偉大なチャンピオン、ロルフv.フォゲルスベルクの血は、ヨーロッパ各国へ広がり、ボクサー犬史の上でも重要な位置を占めることになります。
特にドイツに残った彼の直仔、CH ロルフv.ヴァルハルは、この系統を残すのに大きく貢献し、スイスへ渡ったシェルムv.アンゲルトーァも、その娘が再びドイツに戻り活躍することによって、次代にその血を残すことになります。
さて、ロルフv.フォゲルスベルクは縞しか出さない種牡と言われており、しかも何故か圧倒的に牡に良い犬が多く出ました。
縞しか出さないロルフの仔に、何故牡で優れた犬が多かったのかは判りませんが、この優性遺伝が彼のサイヤーラインを強力に残すことが出来たということに、少なくとも有利に働いたと言われています。
一方で直仔のロルフv.ヴァルハルは毛色、性別に関係なく良い犬を出しましたが、総じて父のタイプを受け継ぎ、これを次代に伝えることに成功したのです。
|
|
CH ロルフ v. ヴァルハル(1911年生まれ・縞)
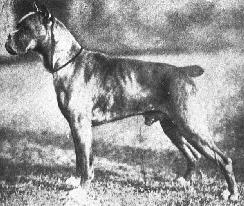 |
CH
ロルフv.フォゲルスベルク |
CH
クルトv.パルツガウ |
CHフーゴv.パルツガウ |
| エルゼv.パルツガウ |
| ヴェヌスv.フォゲルスベルク |
CHホッホシュタインズ・ナーツィ |
| CHフリッガv.フォゲルスベルク |
| ドーラv.フォゲルスベルク |
CH
リーゴv.アンゲルトーァ |
CHシャーニーv.d.パッセージ |
| エラ・ダオエル |
CH
フリッガv.フォゲルスベルク |
CHギガール |
| ムッキーv.d.フォゲルスベルク |
|
|
この犬の血統を一見して言える事は、父のロルフと母のドーラの血統構成が非常に似ているということです。 以下にまとめてみましょう。
|
|
| 父 ロルフの |
母 ドーラの |
| 父方祖父・・・フーゴ |
父方祖父・・・フーゴの全弟、シャーニー |
| 父方祖母・・・ヴォータンの孫娘 |
父方祖母・・・ヴォータンの娘 |
| 母方祖父・・・フーゴの息子 |
母・・・ロルフの母方祖母、フリッガ |
| 母方祖母・・・ドーラの母、フリッガ |
|
|
つまり、お互いの父系が殆ど同じで、母系が全く同じ、したがって母方祖父の系統が違うだけです(ホッホシュタインズ・ナーツィはフーゴの息子、ギガールはヴォータンの息子)。
さて、ロルフv.ヴァルハルが生まれた3年後、ドイツは第1次世界大戦へと突入し、またそれまで父が健在だったこともあって、息子ロルフの繁殖活動は極めて遅くからのもでしたが、それでも6頭のSiegerと5頭のSiegerinを出しました。
ロルフは、父のロルフから伝えられた優れた素質を持ち、父同様弓形の背はありましたが、とりわけ美しいボディを受け継いだと言われています。
ただ頭部はやや小さく、頭部構成、頚部は父に及びませんでした。
ロルフは6歳になってからようやく繁殖のキャリアを積むことができるようになり、1918年生まれのCHモーリツv.ゴールトライン(縞・牡)を筆頭に1921年生まれのSiegerエゴンv.グムベルトゥスブルンネン(茶)まで数々の名犬を老年になってから、しかも短期間で次々と輩出したことには驚かされます。
この中でも特にロルフの特徴を受け継いだのは、縞ではモーリツv.ゴールトライン、茶ではエゴンv.グムベルトゥスブルンネンだと言われています。
|
|
Sieger エゴン v. グムベルトゥスブルンネン (1921年生まれ・茶)
|
残念ながら手持ちの資料不足のため、母の血統がわかりませんが、母のラッセルv.ケンハインはSiegerinで、エゴンの前にもSiegerドリルv.グムベルトゥスブルンネンというエゴンの全兄を出しており、名牝だったようです。
当時の優秀な台牝は、その多くがフーゴ、シャーニ-の兄弟やリーゴ、ミロの血が入っており、ラッセルもまたそうなのかもしれません。
エゴンはSiegerとSiegerinを3頭づつ出しましたが、特にSiegerハンゼルv.シュトルツェンフェルス(茶)、とSiegerエドラーv.イザ-ルストラント(茶)は種牡として活躍しました。しかし残念ながら種牡として活躍することはできませんでした。
エドラーは、その母系が前章に出てきたCHミロv.アイゲルシュタインからSiegerオマールv.ファルケンホルスト、Siegerパッシヤーv.ノイエンベルクと続くレーモス―ミロの貴重な系統で、このパッシャーの娘がエドラーの母犬、ベルフィーネv.イザールストラントです。
|
|
 |
 |
| ハンゼルv.シュトルツェンフェルス |
エドラーv.イザ―ルストラント |
CH モーリツv.ゴールトライン (1918年生まれ・縞)
|
モーリツの母、ダイスィーv.ビーダーシュタインは、スイスに渡ったシェルムv.アンゲルトーァの娘で、シェルムの父はロルフv.フォゲルスベル躯、母方祖父はリーゴv.アンゲルトーァです。従って、モーリツはロルフの(2-3)の近親繁殖犬です。
資料不足のため、ダイスィーの母系はわかりません、ただ、判る範囲で述べれば、父ロルフv.ヴァルハルと母方祖父、シェルムv.アンゲルトーァは共にロルフの息子で、母犬がリーゴの娘ですから、同系での系統繁殖だと言えます。
モーリツの直仔にも数々のタイトル犬がいますが、特にSiegerアレックスv.マクダレーネンクヴェレ、Siegerツェザールv.ドイテンコーフェンは特に種牡として活躍しました。
|
|
CH ツェザール v. ドイテンコーフェン (縞)
|
ツェザールはサイヤーラインを残し、ロルフ-モ-リツのラインを確立したどころか、この系統は長い間独自でイギリスで守られ、4大基礎犬とは別のサイヤーラインをイギリスで築き、1950年代に再びドイツにこの系統が戻り、今日ではこのツェザールの系統が4大基礎犬の系統を翻弄しています。
ツェザールの母、リーゼルv.ドイテンコーフェンは、リーゴの最高直仔、Siegerリーノv.d.エルベ(茶)の娘で、ツェザールは系統的にはロルフの系統でありながらもリーゴの(3・4-3)という近親繁殖犬で、この系統の影響も受けていると言われています。
ロルフv.フォゲルスベルクとリーゴv.アンゲルト-ァの近親計画繁殖の結晶とも言うべきこのツェザールの仔出しは抜群で、Siegerチェックv.フンネンシュタイン(縞)、Siegerグランディv.シュトルツィオ(縞)、Siegerヘルメスv.ビーダ-シュタイン、同胎のハンゼルv.ビーダ-シュタイン、オーストリアSiegerブーコv.ビーダ-シュタイン(茶)等など、種牡としても優れた牡犬を出しました。
特にチェックは、母方祖父にエゴンの全兄、Siegerドリルv.グムベルトゥスブルンネンを持ち、ショーに初めて出たときに、明るい眼色以外は欠点の無い犬だといわれた程で、後に渡米したためにドイツでの直仔は少ないものの、娘にザクトニアス・アントルを残したことで、Siegerinイヴァv.マリエンホーフや4大基礎犬の1頭、Siegerドリアンv.マリエンホーフの母方祖父となりその血を残し、後にはアメリカで初めてボクサーでのBest
in Showを1932年に獲得しました。
また、ヘルメス、ハンゼルの兄弟も共に種牡として活躍し、第二次世界大戦の頃には4大基礎犬の1頭、ルスティッヒの系統と並んで、ドイツの2大系統を築き上げました。
しかし、何と言ってもツェザールの直仔の中で後世に強い影響を及ぼしたのはブーコです。
それは、4大基礎犬の筆頭格である、あのSiegerジグルトv.ドームの父、イヴァインv.ドームを出したことで、最も重要視されて良いのではないかと思います。
ブーコの母は、モーリツの同胎犬、ミラv.ゴールトラインで、つまり父方祖父と母犬が兄妹ということになり、ロルフv.ヴァルハル(3-2)、ロルフv.フォゲルスベルク(4・5-3・4)、リーゴv.アンゲルト-ァ(5・6・4-4・5)という近親繁殖犬ということになります。
|
 |
 |
 |
| チェックv.フンネンシュタイン |
グランディv.シュトルツィオ |
ハンゼルv.ビーダ-シュタイン |
Sieger ブーコ v. ビーダ-シュタイン (縞)
|
さて、1925年にボクサーは勤務犬として承認され、また1914年の第1次世界大戦でロルフv.フォゲルスベルクをはじめとするボクサーがその能力を証明したということは、この犬種の発展の上でも大きな意味があったと思われます。
ミュンヘンのボクサークラブでは、60頭のボクサーを選び、実験として戦場に送り込み、ドーム犬舎のシュトックマン氏は将校としてボクサーの軍犬隊を組織し、その隊長となり、警察犬及びサービスドッグとしての適正を発揮しましたが、使役犬としてはやや小さいことに気付き、1920年には牡犬の体高を60センチに引き上げました。
しかしその当時、ドイツのトップクラスの全てのボクサーが、望ましいとされた大きさの体高には達しませんでした。エゴンの息子エドラーv.イザ-ルストラントは58センチでしたが、これでも当時は大きい方で、優秀なサイヤーラインを広げたツェザールv.ドイテンコーフェンの一族、グランディv.シュトルツィオ、チェックv.フンネンシュタイン、ハンゼルv.ビーダ-シュタイン、皆全て小さかったのです。
|

